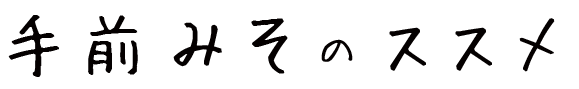普段私が使用している木桶にはそれぞれ歴史があります。
酒蔵からきた木桶、醤油屋からきた木桶など半固形物を仕込む味噌屋は木桶のサイクルの中で一番最後。
県内で作られた木桶もあれば、県外から色々な醸造元を巡ってきた木桶など産地も様々です。
その中でも秋田杉が有名な「秋田」から巡り巡ってきた木桶もたくさんあります。
そんな木桶を通して縁を感じている秋田に念願叶って行くことができました。
味噌屋の夏休み?ですw

いろいろ蔵を訪れる中でたくさんお話しさせていただいた1件目は、秋田県湯沢にある石孫本店さん。
今年頭に行った小豆島の木桶再生プロジェクトで会った数少ない味噌屋さん。
今度秋田行く機会があったら絶対行きますね!って話してたので訪問させていただいちゃいました。
味噌と醤油が半分ずつ、麹室も別にあり昔の設備を今でも大事に活用しながら醸造をされています。
醤油用と味噌用で木桶は別々でしたが、長く大事に使われてきたことがわかるこの木桶の色、落ち着きます。
米の持ち込みでの仕込み味噌のお話しや機械設備、ラーメン屋のお話しなど地域は違っても同業として分かる部分もたくさんあり、とても有意義で温かい時間でした。
最後はそんな蔵、木桶、人から生まれた味噌や醤油の味を頭、体、心に刻みこみました。

2件目は同じ醸造でも酒造りの「新政酒造」さん。
こちらの酒蔵の取り組みや考えを以前から知っていていつか行ってみたいと思って今回お伺い出来た酒蔵です。
温度管理できるタンクが99.9%の酒造り世界で近年逆に全量木桶仕込みに舵をきった新政さんは木桶を使う味噌屋としてぜひお伺いしてみたい蔵元で酒仕込みが始まる前日でしたが快く訪問を受けて下さいました。
醸造の蔵元は歴史が長いこともあり、過去(歴史)の色合いのイメージ?を感じることが多いなか、未来へ向けて歩を進めていると感じることがたくさんあった新政さん。
木桶仕込みは分かりやすい例ですが、道具や蔵・室造りなど色々なところで未来へと繋げるアイデアや挑戦を随所に感じて本当に学びと刺激をたくさん感じました。進化が止まっていない蔵元という感じ。
私も味噌造りでいつも頭にあるのは、どうやったら少しでもいい未来を描けるトライや改善が出来るかということです。
この秋田で聞いたこと、学んだことを活かしながら少しでも未来に向けて挑戦を続けたいです。
PS.十文字ラーメン、横手やきそば、稲庭うどんを今回食べれました!